取材記事の質を担保する取材前後に込めるこだわり
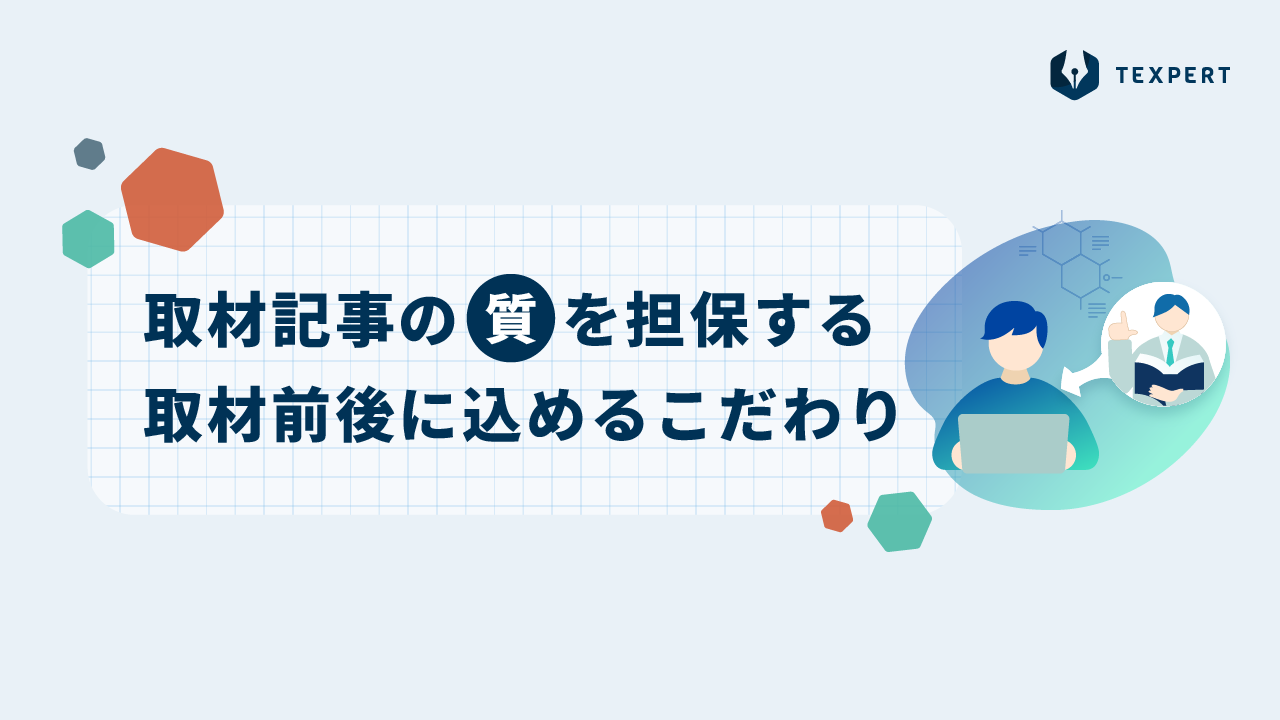
取材・インタビュー記事は人と人とのコミュニケーションによって生まれる考えや感情、閃きを言語化して読者に届けられるコンテンツとして、今注目を集めています。
導入事例や採用インタビューなど、売上アップ・採用・ブランディングなどを目的に取材・インタビュー記事の制作を検討する企業も増えてきました。
一方で、
「取材したはずなのに要点がうまくまとまらない」
「読者が興味を持つ切り口になっていない」
といった課題を抱え、せっかく作った記事を活かしきれていないと悩む企業も少なくありません。
そこで本記事では、「取材記事の質を担保する取材前後のこだわり」をテーマに、取材記事制作に特化する私たちテキスパートが注力しているポイントを紹介します。
取材記事の内製を検討している方も、外注を視野に入れている方も、これから紹介するポイントを実践してみてください。

・取材記事制作を作るうえでの不安が払拭された
・この資料で外注に反対の上司を説得できた
取材記事の質を担保する取材・インタビュー前のこだわり

まずは取材を実施する前にこだわるべきポイントから紹介します。
事前準備が取材の成否、並びに取材記事のクオリティを決めると言っても過言ではありません。
ここでは、ライターの選定から事前準備のポイントまで、取材前にこだわりたい3つの要素を紹介します。
テーマに精通したライターをアサインする
取材記事のクオリティを左右する最も大きな要因のひとつが、担当ライターの知識・経験レベルです。製品やサービス、業界特性を正しく理解し、読者の視点に立った文章表現ができるライターをアサインすることで、完成度を格段に高められます。
- 専門用語への理解
たとえばIT系の導入事例であれば、クラウドやAIなどの知識をある程度押さえているライターの方が、取材相手との会話をスムーズに進められ、適切な質問を投げかけやすいです。取材対象者も「この人は私の話を理解してくれている」とインタビュアーに対して安心感を持てれば、より深い話をしてくれるでしょう。 - 対象読者と目的に合わせた執筆スタイル
採用インタビューでは求職者に魅力が伝わるような語り口やエピソードの引き出し方が重要。一方でBtoB領域の導入事例では、ビジネス視点での課題やROIなど、数字面の切り口が重視されます。
ライター選定のポイント
- 過去の執筆実績: 同じ業界や類似テーマの実績があるか
- 取材力: 「配慮はするが遠慮はしない」を実践し記事として欲しい情報を引き出せるか
- 文章力: 読者が理解しやすいように用語や背景を噛み砕いて記事化できるか
目的とゴールの共有
ライターが決まったら、取材の最終的な目的やゴールを明確に共有することが次のステップです。
導入事例なら「新規顧客の購買意欲を高める」、採用インタビューなら「求職者が自社の魅力をイメージしやすくなる」など、何を目指すのかを関係者全員が共通認識を持つことが大切です。
- 読者像の明確化
例えば採用インタビューの場合、「新卒向けなのか、中途採用なのか」「学生に近いフランクな言葉遣いか、社会人向けのビジネスライクなトーンか」といった点で、記事の書き方が変わってきます。 - 記事で伝えたいコアメッセージ
自社のビジョンや、サービスの強み、社員の働く姿勢などを明確にし、ゴールに沿ったメッセージを統一することが重要です。
こうした情報をライター・ディレクターに正確に伝えておくことで、ブレのないコンテンツ設計が可能になります。
徹底した事前リサーチと質問リストの作成・共有
質の高い取材を実現するためには、事前リサーチが欠かせません。
取材相手の背景や業界動向、過去のニュースリリースなどをしっかり読み込むことで、相手に応じた適切な質問を準備できます。
また、取材相手がSNSを運用している場合は、過去の投稿まで遡って目を通し、考え方や最近起きた出来事などをインプットします。
- 背景理解: 取材相手の企業・組織の沿革やサービスの特徴を把握する
- 課題と期待値の把握: なぜ取材が必要なのか(例:新製品PR、成功事例の共有、採用ブランディングなど)
- 質問リストの作成と優先度設定: 「必ず聞きたい内容」「時間があれば聞く内容」に分けるとスムーズ
また、質問リストを事前に共有しておくことで、取材相手も回答を整理しやすくなり、限られた時間で効率的に情報を得られます。ただし、あまり細部まで固めすぎると予定調和のやり取りになりがちなため、余白を残して臨機応変に掘り下げられるようにするのがポイントです。
取材が途中で脱線することの重要性はこちらの記事でも解説しています。
取材・インタビュー後のこだわり

次は取材後です。
良い取材ができていることはもちろん大前提ですが、取材の内容を生かすも殺すもこのフェーズですべて決まります。
2名体制での編集
取材後の原稿制作では、ライターとディレクターの2名体制を敷くことで、品質を高めることができます。ライターは取材した内容を記事に落とし込み、ディレクターはそれを客観的にチェックする役割を担います。
- ライターの役割
- 取材内容を踏まえ、読みやすい文章にまとめる
- インタビュー相手の言葉遣いやニュアンスを生かしつつ、読者に伝わりやすい文章へ再構成
- 適切な見出し設定や情報の取捨選択
- ディレクターの役割
- 原稿全体を第三者視点でチェックし、内容や構成がターゲットやゴールに合っているかを確認
- 必要に応じて構成変更や加筆修正の提案
- 校正・校閲作業(事実関係や誤字脱字の確認)
こうした分担によって、取材時に得た情報の熱量と、客観的な読みやすさを両立させることができるのです。
ディレクター(編集者)が記事納品前にさらにチェックすべきポイント
- 読者が理解しやすい流れか
取材相手の話を時系列やテーマごとに整理し、読み進めやすいかどうか。 - 不要な情報・説明不足の情報はないか
業界用語の解説を入れるべきか、読者の興味を削ぐような余分な情報がないか。 - トンマナ(文体・表現)が統一されているか
ゴール設定やターゲットの属性に合わせた文体・用語が選ばれているか。 - 事実関係の確認
数値や名称、部署名などが正しいか、根拠が曖昧な表現はないか。
ライターとディレクターが互いに役割分担して責任を持つことで、取材後の原稿クオリティを高い水準で保つことができます。
取材前後のこだわりが記事の質を左右する
良質な取材記事を制作するうえで、取材が重要であることは言うまでもありません。
しかし、それを記事にしたときに読者が最後まで読み、心動かされるものになるかどうかは前後のこだわりが物を言います。
如何に「神は細部に宿る」を徹底できるかです。
取材記事の内製している方は今回紹介したこだわりポイントを漏れなく実践できる体制づくりを、外注を検討している方は、これらを実践できる外注先を探してみてください。

・取材記事制作を作るうえでの不安が払拭された
・この資料で外注に反対の上司を説得できた

