読者のストレスをゼロに!一文単位でこだわる文章編集術を紹介

良い取材・インタビュー記事を制作するためには良い取材が不可欠なのは当然ですが、それと同じくらい大切なのが「その後の文章制作」です。
せっかく良い取材ができてもそれをわかりやすい・面白い記事に仕上げられなければ、読者には届きません。
そして、読者に最後まで読んでいただける記事を作るためには、読者が
- 読んでいて違和感を抱く
- 途中で引っかかる
- 解釈が分かれる
といった、ネガティブな要素を徹底的に排除することが最も重要です。
本記事では、読者が最後までスラスラ読み進められる記事を作るための
”こだわりの文章編集術”
を紹介します。
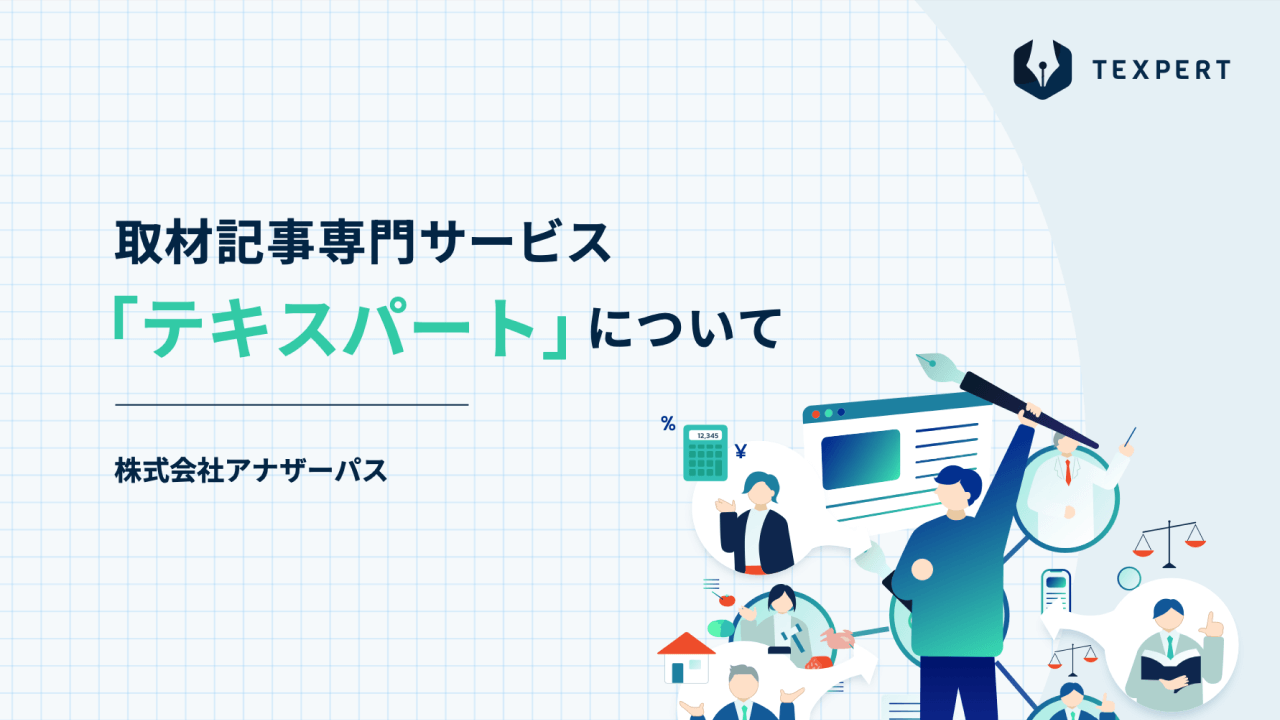
・取材記事制作を作るうえでの不安が払拭された
・この資料で外注に反対の上司を説得できた
最後まで読まれる記事を作るための15のチェックポイント
さて、テキスパートが記事制作をする際に意識しているポイントを厳選して15つ紹介します。
同じ語尾を連続させない
文章は全体として読んだ時の”リズム””抑揚”が大切であり、これらは文章の読みやすさ・説得力に大きく影響します。
同じ語尾を連続で使用してしまうと、その部分が単調なリズムになり、読者は読みながら違和感を抱きます。また、同時に稚拙な印象も与えてしまい、内容の説得力も下がります。
語尾には基本的な「~です。」「~ます。」のほかにも、「~ません。」「~でしょうか。」「~しょう。」、または「体言止め」など複数の実践的に使用できる語尾があるので、意識的に使い分けるようにしています。
| NG | アルバイトを探すうえで「バイトをする目的」をはっきりさせることが大切になります。目的もなくアルバイトを始めると、自分の性格やライフスタイルに合わず、すぐに辞めることになってしまうこともあります。まずは目的をはっきりさせてから、自分に合ったアルバイトに応募することをおすすめします。 |
| OK | アルバイトを探すうえでは、「バイトをする目的」をはっきりさせることが大切です。目的もなくアルバイトを始めると、自分の性格やライフスタイルに合わず、すぐに辞めることになりかねません。まずは目的をはっきりさせてから、自分に合ったアルバイトに応募することをおすすめします。 |
| NG | 私たちは、ふとした瞬間に「懐かしさ」という感情に心を奪われるときがあるものです。この懐かしさの正体とは、いったいどのようなものなのかを考えると面白いです。懐かしいという感情が、私たちにもたらしてくれるものとは?今回は、改めて「懐かしさ」の感情について考察していく記事です。 |
| OK | 私たちは、ふとした瞬間に「懐かしさ」という感情に心を奪われるときがあります。この懐かしさの正体とは、いったいどのようなものなのでしょうか?懐かしいという感情が、私たちにもたらしてくれるものとは?改めて「懐かしさ」の感情について考察していきます。 |
同じ助詞を連続させない
助詞も意識していなければつい連続させてしまいがちですが、これも読者に単調な印象を与え、内容に対する説得力を下げます。
基本的に二回の連続であれば許容範囲と考えますが、三回以上からは明確に文章が読みにくくなります。
| NG | “違う”という言葉の類似の表現の種類はたくさんある。 |
| OK | “違う”という言葉に似ている表現の種類はたくさんある。 |
| NG | 留学生活は基本的には一人では過ごすことはできない。 |
| OK | 留学生活は基本的に一人で過ごすことはできない。 |
| NG | 従業員に急に取引先に行くように指示するのは良くない。 |
| OK | 従業員に突然取引先の元へ行くように指示するのは良くない。 |
| NG | これが私がおすすめする料理だが、みんなが反対する。 |
| OK | 私のおすすめの料理はこれだが、みんなは反対する。 |
語尾は極力シンプルにする
前述の通り、語尾は抑揚を持たせるためにバリエーションを豊富にすべきですが、”長さ”に関しては一般的には短い方が読みやすいです。
同じ意味なのであれば文字数は極力少ないほうが読者の負担が小さくなるからです。
| NG | ワーキングホリデービザでは滞在中に制限なく働くことが可能です。 |
| OK | ワーキングホリデービザでは滞在中に制限なく働けます。 |
| NG | 海外留学では英語を学ぶことができます。 |
| OK | 海外留学では英語を学べます。 |
| NG | 非常に困難な状況となっております。 |
| OK | 非常に困難な状況です。 |
同じ表現を乱用しない
話すときも書くときも、人はつい使い慣れた表現を多用しがちです。
しかし、文章制作において同じ表現を連続して使用することは、読者に単調・退屈な印象を与えます。
同じ意味でもなるべく表現にバリエーションをもたせることで、読者が途中で飽きることがないようにします。
| NG | 実際にお店にお越しいただき、施術をお受けいただいた後は、スタッフが行うマッサージによってリラックスしていただけます。※理由:「~いただく」という表現が連続している |
| OK | 実際にお店にお越しになり、施術をお受けいただいた後は、スタッフが行うマッサージによってリラックスできます。 |
| NG | 料理店ABCの目玉メニューは「なつかしのナポリタン」であり、実際の口コミ評価でも美味しいと好評です。秘伝のトマトソースにピーマン、熟成させたウインナー等のこだわりの具材を混ぜ合わせることで、昭和の食堂のような味わいに仕上げられています。また、同じく店主おすすめのメニューが「豆腐のハンバーグ」です。豆腐を使ったヘルシーな味わいであり、秘伝のデミグラスソースが濃厚な味わいを実現。一度食べれば病みつきになってしまう美味しさです。 ※理由:「美味しい」「味わい」「秘伝」を多用。 |
| OK | 料理店ABCの目玉メニューは「なつかしのナポリタン」であり、実際の口コミ評価でも「昔懐かしい味を堪能できる」と好評です。こだわりのトマトソースにピーマン、熟成させたウインナー等のこだわりの具材を混ぜ合わせることで、昭和の食堂のような味わいに仕上げられています。また、同じく店主おすすめのメニューが「豆腐のハンバーグ」です。豆腐を使ったヘルシーでライトな口当たりに加え、秘伝の濃厚デミグラスソースで舌鼓を打つ体験ができます。一度食べれば病みつきになってしまう美味しさです。 |
異音同義語を覚えるべし
先程の「同じ表現を乱用しない」に関わってきますが、同じ意味を持つが異なる言葉・表現を多く知っておくことで、文章にバリエーションが持たせられるほか、硬い文章・カジュアルな文章など、さまざまな種類の記事制作に対応できます。
豊富な表現が使用されていることで、読者も常に刺激を受けながら読み進められ、飽きがきません。
| 言葉① | 言葉② |
| 持つ | 有する |
| 違う | 異なる |
| 必須 | 必要 |
| 達成 | 成就 |
| 作る | 築く |
| 支障 | 弊害 |
| 企業 | 会社 |
| 方法 | 手段 |
横文字を乱用しない
横文字は非常に使い勝手が良く、一見”カッコイイ”印象があるのですが、全体的に言葉の抽象度が高く、文章全体も意味の曖昧なものになりがちです。
日本語で表現できる単語があるのであれば、極力横文字は使用せず日本語で書くことを意識しています。
| カタカナ言葉 | 日本語 |
| コンセンサス | 同意、賛成 |
| コミット | 頑張る |
| エビデンス | 証拠 |
| アジェンダ | 題目 |
| ペンディング | 中断 |
| アサイン | 任命 |
| マター | 問題 |
| ブラッシュアップ | 研究、調査 |
重ね言葉を使わない
わかりやすい例えが
「車に乗車する」
「頭痛が痛い」
です。
ここまであからさまだとさすがに気づくのですが、意外と重ね言葉を使用していることに気づかないケースがあります。
話し言葉としては一般的に使用されてしまっているばかりに、重ね言葉を使用しても読者が気づかないこともありますが、やはり文法上は誤りなので決して使用しません。
| NG | あらかじめ予定していた通りに実行します。 |
| OK | 予定していた通りに実行します。 |
| NG | 8月にカナダに留学するのが一番ベストです。 |
| OK | 8月に留学するのがベストです。 |
聞き慣れない単語の使用は避ける
”聞き慣れない単語”を定義するのは難しいのですが、ここでは「普段の会話でほとんど使われることのない単語」と捉えます。
小説や論文であればやや難解、もしくはあまり一般的に使用されない単語を用いることも一つの手段です。
しかし、「わかりやすさ」が最も重視される取材・インタビュー記事においては、読者フレンドリーを意識し”日常会話で使用されるレベルの単語”を優先的に使用します。
| NG例 | OK例 |
| 鳥瞰する | 俯瞰する |
| 刹那 | 瞬間 |
| 蛇足 | 無駄 |
| 成就 | 達成 |
| 万障 | 支障 |
| 至極 | 極めて |
何にでも使える動詞は使用を避ける
- する
- 行う
といった動詞を指します。
これらは便利故、あらゆる文脈で使用できてしまいます。
しかし乱用は文章に稚拙な印象をもたらすため、極力使わず動詞にもバリエーションをもたせます。
| NG | ABCレストランは今年の夏に新たなメニューの打ち出しをしています。接客に関するスタッフの教育もします。価格の改訂もするようで、よりリーズナブルな価格でお客さんが料理を楽しめるよう、さまざまな工夫をします。 |
| NG | ABCレストランは新たなキャンペーンを行い、より多くの人に来店してもらえるようさまざまな取り組みを行っていきます。価格の改訂や食材の再選定も行い、根本的な店としてのあり方の見直しも行っていきます。 |
一文の長さを適切にする
一文が短すぎるとぶつ切りの箇条書きのようになり、反対に一文が長すぎても終わりが見えずその文が何を伝えたいのかわかりづらくなってしまいます。
よって、一文の長さは80~100文字以内に抑えるようにします。
ポイントは、「音読したときに苦しくならないか」です。
途中で苦しくなるようであれば、それは一文が長すぎるサインです。
一文内で主語が変わらないようにすべし
一文内で主語が変わることは日常会話ではよく起こります。
会話であればその場の雰囲気や前後の文脈で正しく理解できるのですが、文章にすると混乱を招きます。
なるべく”一文一主語”にするよう意識し、一文内で主語を複数使用する場合は省略せず、必ず明記することを徹底します。
| NG | ABCレストランは素材にこだわった上質な料理を提供しており、心ゆくまで堪能できます。 |
| NG理由 | 読点(、)の前は主語が”ABCレストラン”ですが、読点の後は急に主語が来店客に変わっており、さらにそれが明記されていません。 |
| OK | ABCレストランは素材にこだわった上質な料理を提供しており、訪れた人は心ゆくまでその料理を堪能できます。 |
| OK | ABCレストランは素材にこだわった上質な料理を提供しています。訪れた人は心ゆくまでその料理を堪能できます。 |
文章の濃度を上げる
取材・インタビュー記事をはじめとした、情報提供を目的としたコンテンツは、読者の負担を最小限にする工夫が求められます。
その一つとして、
「最小の文字数で最大の情報を読者に提供する」ことを私たちは意識します。
| NG | AIが普及することのデメリットは主に二つあると考えられます。一つ目は雇用が減少することです。AIによる単純作業の処理が当たり前になれば、事務職やレジ打ち店員等の職業は必要なくなってしまうと考えられるからです。二つ目は、責任が誰にあるのかがわからない、ということです。AIが原因の事故や事件が起こってしまった場合、その責任はAIを開発した人なのか実際にAIを使用した人なのか、明確に判断することは難しいと言えるでしょう。AIが普及していくことのメリットを享受するとことと同時に、デメリットを打ち消すための施策を考える必要があると言えます。 |
| OK | AI普及のデメリットは主に二つ考えられ、一つは雇用の減少です。AIによる単純作業の処理が当たり前になれば、事務職やレジ打ち店員等の職は不要になると考えられるからです。二つ目は、責任の所在の不明瞭さです。AIに起因する事故や事件が発生した際、その責任は開発者なのか使用者なのか、明確な判断が難しいでしょう。AI普及のメリットを享受すると同時に、デメリットを打ち消す施策の考案が必至と言えます。 |
表記揺れを排除する
同じ単語でも送り仮名が違ったり、複数の表記方法(平仮名/カタカナ/漢字)があったりする場合、同サイト・記事内では表記を必ず統一します。
文章の質に直接影響するわけではありませんが、表記ゆれが目立ってしまうと、読者に「雑な記事である」という認識を持たれ、内容の説得力に影響します。
表記ルールはクライアント各社様によって異なるため、制作開始前にレギュレーションの有無を必ずお客様に確認させていただいています。
| いぬ | イヌ | 犬 |
| ウェブライター | Webライター | WEBライター |
| 取組 | 取組み | 取り組み |
| 売上 | 売上げ | 売り上げ |
| ひとつ | 一つ | 1つ |
同じ接続詞を連続で使用しない
同じ接続詞を連続で使用してしまうと、文としてのリズムが単調となり、読んでいて飽きが来ます。
異音同義の接続詞を用いることで文がシンプルになり、読みやすくなります。
| 添加 | |
| NG | ABCレストランでは美味しいフレンチを食べられます。そして、イタリアン料理も非常に人気です。そして、接客も非常に丁寧で何度でも足を運びたくなります。 |
| OK | ABCレストランでは美味しいフレンチを食べられることに加えて、イタリアンも非常に人気です。さらに、接客も非常に丁寧で何度でも足を運びたくなります。 |
| 逆説 | |
| NG | ABCレストランは東京でも高い人気を誇るフレンチレストランです。しかし、最近は近くでライバル店がオープンしたことで、徐々に客足が遠のいているようです。しかし、その状況を打破すべく、新たなメニューを続々と打ち出しています。しかし、あまり結果が振るわず、より効果的なキャンペーンを実施する必要がありそうです。 |
| OK | ABCレストランは東京でも高い人気を誇るフレンチレストランです。しかし、最近は近くでライバル店がオープンしたことで、徐々に客足が遠のいているようです。それでも、その状況を打破すべく、新たなキャンペーンを打ち出しているようですが、あまり結果が振るわず、より効果的なキャンペーンを実施する必要がありそうです。 |
取材で使われた言葉をそのまま使用することにこだわらない
これは取材・インタビュー記事特有のテクニックです。
取材でインタビュアー・インタビュイーが発した言葉をそのまま文章に使用すると、その現場にいた人にしか意味が伝わらないケースが往々にしてあります。
会話では、相手が発した言葉に多少言葉足らずであったり、表現が曖昧な部分があったりしても、聞いた相手は前後の文脈やその場の雰囲気で内容を脳内補完できます。
しかし、これをそのまま文章にした途端に意味が伝わりづらくなるのです。
最後まで読んでもらえるわかりやすい取材記事を作るためには、相手の言葉を最も読者に伝わる表現に変更して記事化することもあります。
もちろん、インタビュアーが元々の言葉・表現に強いこだわりをお持ちの場合は、その表現自体は変えず、前後の文章に手を加えることで、意図が確実に伝わるような編集を行います。
インタビュイー(取材を受ける人)の個性を活かす文章制作術については、以下の記事でも詳しく解説しています。
”神は細部に宿る”を徹底する文章制作術
私たちテキスパートが文章に込めるこだわりの一部を紹介しました。
今回お伝えしたものは氷山の一角で、こだわりを挙げればキリがありません。
また、読者の方からすれば「そんなのどっちでもいいよ」というものもあったかもしれません。
しかし、一見するとどちらでもいい、違いのわかりにくい細部へのこだわりが面白い記事を作り、それが読者の心を動かしたり、悩みを解決したり、行動を後押ししたりします。
細部にまでこわった取材・インタビュー記事を作りたいとお考えでしたら、ぜひ私たちテキスパートにご相談ください。
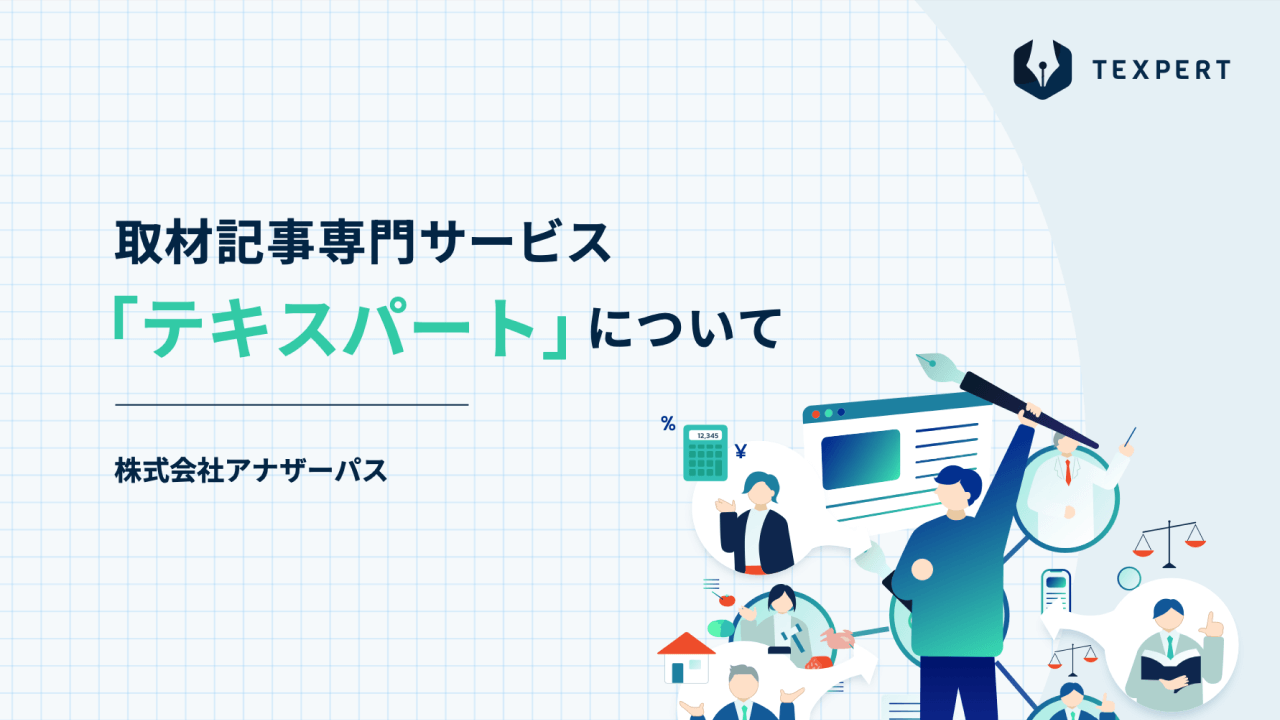
・取材記事制作を作るうえでの不安が払拭された
・この資料で外注に反対の上司を説得できた

