社員インタビュー記事で採用活動を加速!おすすめの代行会社も紹介

採用市場が激化する中で、応募者の目に留まる企業になるためには、“企業のリアルな姿”を魅力的に発信していくことが欠かせません。
近年は、会社のHPやSNS、求人サイトなどで「社員インタビュー記事」を公開する企業が増えており、求職者が職場の雰囲気や社員の想いを掴みやすくなっています。
しかし、上記のようなトレンドから、自社でも社員インタビュー記事を作って応募者を増やしたいと思ったとしても
「本当に効果があるのかわからない」
「そもそもどうやって作ればいいのかわからない?」
「インタビューする社員は空いている人を適当に選んで15分くらい話せばいいの?」
など、様々な疑問を解消できず、制作に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、社員インタビューを作ることによって期待できるメリット、具体的な作り方を紹介します。

・取材記事制作を作るうえでの不安が払拭された
・この資料で外注に反対の上司を説得できた
社員インタビュー記事を取り入れるメリット

SNSを用いた発信やオフラインの説明会など、採用活動を目的としたコンテンツやアクティビティは多数あります。
まずは、その中でも社員インタビュー記事を取り入れるメリットから紹介していきます。
企業のリアルな雰囲気を伝えられる
社員インタビュー最大の魅力は、企業の公式情報や求人票だけでは伝わりづらい「職場のリアル」を求職者へ届けられることです。
たとえば、「実際の業務内容」「社員同士のコミュニケーション」「仕事に対するやりがいや苦労」など、当事者でなければ語れないエピソードを記事にして紹介します。
すると、この”疑似入社体験”を通じて、求職者はその会社で働く姿をより具体的にイメージできるのです。
ミスマッチを減らし、早期離職のリスクを下げる
採用において、入社する人数を増やすことと同じか、それ以上に重要なのが離職率を下げることです。
多大なコストと時間をかけた採用活動を通じて、せっかく多くの社員が入社してくれても、その後すぐに退職されてしまっては本末転倒です。
離職の主な原因の一つに、入社前後のギャップがあります。入社前に描いていた働き方や業務内容と、入社後の実際のそれがあまりに異なっているために早期離職を決意してしまうのです。
アデコグループの調査では、「自身の希望と業務内容のミスマッチ」(37.9%)が早期離職の主な理由の一つとして挙げられています。
参考:アデコグループ「新卒入社3年以内離職の理由に関する調査」
https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/061
そうしたギャップ、ミスマッチを防ぐうえでも社員インタビュー記事が役立ちます。
社員の声を通じて、“いい面”だけではなく“リアルな課題や大変な部分”も発信することで、求職者は入社前からその企業に対して正しい印象を持ちます。入社後の悪い意味での”ギャップ”に直面することがなくなり、結果的に高い定着率が期待できるのです。
求職者の興味を引き、応募数を増やす
社員インタビュー記事は、会社のホームページや採用サイトではなかなか醸し出せない良い意味での「非公式感」が読者に親近感を抱かせ、会社に対して興味を持つきっかけづくりをしてくれます。
記事に載っている社員の考えやキャリア観などに共感が集まれば、その記事がSNSでシェアされる確率も高まり、さらなる認知拡大が期待できます。
企業ブランドの向上・差別化
求職者が企業を選ぶ際、「社風が自分に合いそうか」「成長環境が整っているか」「働く仲間に魅力を感じるか」といった点を重視するケースが増えています。
株式会社リクルートマネジメントソリューションズが2024年卒の大学生を対象に行った調査によると、内定承諾の最終的な理由として、
「自分のやりたい仕事(職種)ができる」が15.1%で最多となり、
次いで「社員や社風が魅力的である」が9.2%となっています。
参考:リクルートマネジメントソリューションズ「「2024年新卒採用 大学生の就職活動に関する調査」の結果を発表」
https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/0000000421/
社員インタビューを通じて、企業の価値観やカルチャー、社員が大切にしている働き方を発信することで、他社との違いを明確に示すことができます。
また、社員が自社の魅力を自然に語る姿を見ると、外部からは「社員が誇りを持って働いている会社」というポジティブなイメージが伝わりやすくなり、企業のブランド力向上にも寄与します。
社内エンゲージメントの向上
インタビューを受ける社員自身も、自分の仕事を振り返る良い機会になります。
普段意識していなかった自身や会社の強みややりがいを言語化することがモチベーションアップにつながったり、自社に対する誇りが強化されたりします。
さらに、公開された自身のインタビュー記事が社内で共有されれば、部署間の理解が深まったり、他の社員も自分が働く会社の良さを再認識できるでしょう。
複数の媒体で活用できる
社員インタビュー記事は、一度制作すればさまざまな媒体で活用できる点も大きな魅力です。
自社の採用サイトに掲載するだけでなく、求人媒体やオウンドメディア、プレスリリース記事、さらにはSNS投稿や会社案内パンフレットへの二次利用も可能です。
複数のチャネルで発信することで、より多くの求職者の目に触れやすくなり、採用活動全体の効果を高められます。
社員インタビュー記事の作り方
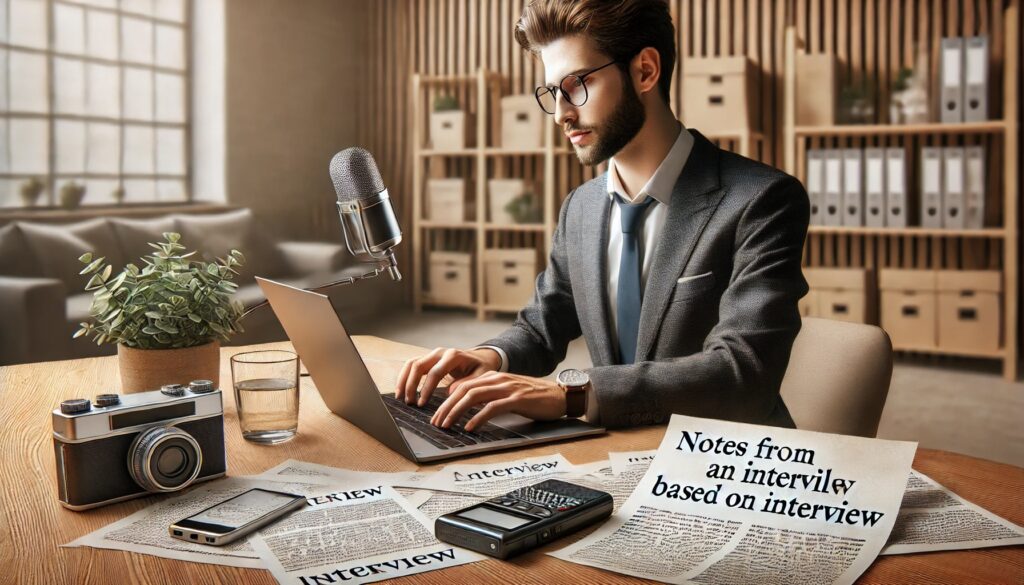
社員インタビュー記事は、ただ“質問に答えてもらう”だけでは十分な効果が得られません。
求職者が読んで興味を持ち、応募や入社後の活躍へつなげるためには、「どのように作るか」がポイントになります。
目的・ターゲットを明確にする
まずは、社員インタビュー記事を作る目的とターゲットをはっきりさせましょう。
- 目的:応募者に自社の魅力を伝える、新卒採用をメインにPRしたい、中途採用向けにキャリアアップの可能性を伝えたい、など
- ターゲット:新卒か中途か、エンジニアなど専門スキルを持った人材なのか、20代若手なのか、など
目的とターゲットが定まると、インタビュー記事の内容や質問の方向性も決めやすくなります。
インタビューする社員を選ぶ
ターゲットに近い属性や役割を持つ社員を選定することが効果的です。
例えば、新卒向けなら若手社員や入社3年以内の社員、中途採用向けなら未経験転職やキャリア転職を経験した社員をインタビュー対象にすると、求職者は「自分もこうなれるかも」とイメージしやすくなります。
また、インタビュイー(取材対象者)自身が何らかの強みや成功体験、苦労話を持っていると、内容に深みが生まれ読み応えのある記事となります。
質問内容・構成を工夫する
インタビューのクオリティは、事前準備の質によって大きく左右されます。
記事のテーマやターゲットを踏まえつつ、あらかじめ質問項目を整理しておきましょう。
- 質問例
- 入社のきっかけ・動機
- 現在の仕事内容とその面白さ・やりがい
- 大変なことや課題、乗り越え方
- 会社のカルチャー・雰囲気
- 今後の目標やキャリアパス
- 入社を検討している人へのメッセージ
構成としては
「プロフィール紹介 → 入社前後のギャップ → 現在の業務内容・やりがい → 今後の目標 → 読者へのメッセージ」
などの流れにすると、読みやすく求職者にとって必要な情報を整理しやすくなります。
写真やビジュアルを活用する
テキストだけでは伝わりづらい雰囲気を、写真や動画、イラストなどを使って補完するのも効果的です。
社員の表情、職場の風景、仕事風景などを一緒に載せると、読者が記事の内容をイメージしやすくなります。
- インタビュー風景の写真や、普段のオフィスの様子
- 社員がチームで働いているシーン
- デスク周りや愛用アイテムの紹介
ビジュアル情報があると、読了率が上がりやすく、SNSでシェアされる確率も高くなります。
適切な長さと読みやすさを意識する
社員インタビュー記事は、あまりにも長すぎると最後まで読まれにくくなります。
一方で、短すぎると企業の魅力がうまく伝わりません。インタビュー内容を整理し、適宜見出しや段落を入れつつ、読みやすい構成を心がけましょう。
- 箇条書きや強調(太字)などを上手く使う
- 一つの段落を長くしすぎない
- 目次や見出しで読者がどこを読めばいいか把握できるようにする
社員インタビューの公開場所を検討する
社員インタビュー記事は、次のような場所に掲載し、多くの人の目に触れるようにしましょう。
- 企業の採用サイト内の「社員インタビュー」ページ
- コーポレートサイトのブログやニュースページ
- 採用系メディア(Wantedlyやリクナビなど)の特設ページ
- 企業公式SNSでのシェア・拡散
公開した後も、社内や取引先、学生向けのイベントで紹介したり、求人の説明会資料にリンクを挿入するなど、幅広く活用するとより効果的です。
社員インタビュー記事を外注するメリット・デメリット
社員インタビュー記事を作ろうと考えた時、挙げられる手段としては内製するか外注するかの二択が基本となります。
ここでは、社員インタビュー記事制作を外注することのメリット・デメリットをそれぞれ解説します。
外注のメリット
まずは外注のメリットから紹介します。
プロによる取材・執筆で質の高い記事を制作できる
外注することによる何よりのメリットは、取材や執筆のプロに任せられる点です。
経験豊富なディレクターやライター兼インタビュアーが制作を担うことで、読みやすく構成の整った記事を制作できます。
採用候補者にとって魅力的に映る記事に仕上がるため、自社の雰囲気や社員のリアルな声を効果的に伝えやすくなります。
しがらみのない第三者の視点でインタビュイーの魅力を引き出せる
社内での取材では、どうしても上下関係や利害関係が影響しやすく、社員が本音を話しにくいこともあります。
外部のインタビュアーが関わることで、フラットな立場から質問でき、社員の自然な発言や想いを引き出しやすくなります。
その結果、読者にとって共感度の高い記事を作れる点が大きな強みです。
採用担当者の負担を軽減できる
採用担当者が自ら取材や執筆を行う場合、通常業務と並行することになり、大きな負担となります。
外注すれば、取材準備や執筆、編集などの工数を外部に任せられるため、担当者は採用戦略や候補者対応といったコア業務に集中できます。
結果的に採用活動全体の効率が上がる点も見逃せません。
外注のデメリット
ここまでは外注のメリットを紹介してきましたが、一方でデメリットも存在します。
費用がかかる
外注には当然ながらコストが発生します。
記事1本あたり数万円から十数万円が一般的な相場であり、制作会社やライターによって料金体系は大きく異なります。
採用広報にどれだけ予算を割けるかを事前に検討し、費用対効果を見極めることが重要です。
日程調整や記事の修正などに時間がかかる可能性がある
外注をすれば何もせずともすぐに記事が完成するわけではありません。
取材対象者との日程調整や記事の確認・修正のプロセスが発生し、その過程で依頼企業が関わらなければならない場面は必ず発生します。
特に記事の初稿に修正依頼が多い場合、完成までに時間が延びる可能性があります。そのため、余裕を持ったスケジュール設定と、外注先とのスムーズなコミュニケーション体制が求められます。
社員インタビュー記事制作の依頼先の決め方
外注のメリット・デメリットの双方を理解したうえで外注を決めた時、次にすべきは「どこに依頼するか」を選ぶことです。
ここでは、外注先を選ぶうえで見るべきポイントを紹介します。
制作実績の豊富さを見る
まず確認したいのが「制作実績」です。社員インタビュー記事の制作に慣れている会社であれば、企業の雰囲気を的確に伝えるノウハウを持っています。
公式サイトや制作実績ページを確認し、どのような業界や企業の事例を手がけているかを比較しましょう。
対外的に公開していない(できない)実績を持つ企業も多いので、外注先候補の企業と打合せをする機会があれば聞いてみましょう。
料金体系は明瞭か
料金体系のわかりやすさも、依頼先を選ぶ上で重要なポイントです。
基本料金に含まれる範囲(取材・執筆など)が不明確だと、後から追加費用が発生して想定以上のコストになることもあります。
見積もりの段階で「何が含まれていて、何がオプション扱いになるのか」を明示してくれる会社を選ぶことで、安心して依頼できます。
複数社を比較し、費用対効果を見極めることが大切です。
安心できる制作体制を構築できているか
社員インタビュー記事は、単なるライティングではなく、取材前の準備から当日の進行、記事公開まで多くの工程があります。
安心して任せられる制作体制が整っているかどうかも確認しましょう。
たとえば、ライターとディレクターの二重チェック体制があるか、修正対応のプロセスが明確か、進行管理を任せられるかなどです。
こうした体制が整っている会社なら、クオリティを担保しつつスムーズにプロジェクトを進めることができます。
おすすめの社員インタビュー記事制作会社7選
ここからは、社員インタビュー記事の外注先としておすすめの企業を7社厳選して紹介します。
テキスパート(株式会社アナザーパス)
手前味噌で恐縮ですが、私たち株式会社アナザーパスが運営する取材・インタビュー記事制作に特化したサービスです。
まず業界でも珍しく、取材・インタビューの記事制作に特化しています。
また、すべての取材現場にディレクター・インタビュアーの二名体制で伺い、インタビュアーがメインで取材を実施、ディレクターはその補佐を行うという万全の体制です。
修正回数も無制限で対応させていただくので、妥協のない”最後まで読まれる面白い記事”を制作できます。
株式会社声音
株式会社声音は「声を未来に残す」という理念を掲げ、取材対象者の考えや思いを丁寧にすくい上げ、魅力的なコンテンツとして形にしてくれるサービスを展開しています。
取材記事の制作にとどまらず、ブランディングの一環としてメディアの企画・運営までサポートしており、幅広い領域で心強いパートナーとなってくれます。
さらに、公式サイトに掲載されている制作実績も豊富で、企業経営者のインタビューだけでなく、芸能人や著名人への取材経験も多数あります。
株式会社アサック
株式会社アサックは、大阪を拠点に昭和50年から続く、長い歴史を持つ企業です。導入事例や社内報、社員インタビューをはじめ、学校案内や統合報告書・環境報告書など、幅広いジャンルの取材コンテンツ制作に対応しています。
さらに、カメラマンによる撮影、誌面やWebのデザイン、記事の更新といった多彩なオプションサービスも提供しており、ワンストップで依頼できる点も強みです。
また、公式サイトにはインタビュアーのプロフィールが掲載されており、15〜25年の豊富な経験を持つプロが取材を担当してくれるため、安心して依頼できる体制が整っています。
株式会社アプリオリ
株式会社アプリオリは、メディカル&サイエンス分野に強みを持つデザイン・翻訳会社です。そのため、医療関連やBtoB領域での経験豊富なライターが取材・執筆を担当してくれるのが特徴です。
医療以外の幅広い分野でもインタビュー記事の制作に対応可能で、柔軟に依頼できます。
さらに、個別インタビューはもちろんのこと、座談会や対談形式、複数人を対象とした取材など、多様なスタイルのインタビュー記事制作にも対応している点が強みです。
https://apriori-inc.co.jp/service/design/interview.html
SHUTTER Location Photo Service
SHUTTER Location Photo Serviceは、法人向けに企業ホームページや会社案内の制作を手がけるほか、近年は採用サイト向けのインタビュー記事にも力を入れているサービスです。雑誌や書籍編集で培った豊富な経験を活かし、質の高い原稿を提供してくれます。
料金体系は「スピードプラン」「ミディアムプラン」「プレミアムプラン」の3種類に分かれており、それぞれ40,000円、100,000円、120,000円とわかりやすい固定価格が設定されています。
取材ライタープロ
取材ライタープロは、株式会社Webライタープロが運営する取材記事制作サービスです。株式会社Webライタープロはライティングのスペシャリスト集団として、SEO記事から取材記事まで幅広く手掛けています。
このサービスでは、1記事からのトライアル発注も可能なため、本格的な依頼の前のお試しもできます。
また、取材に特化したライターが取材・ライティングを担当するほか、ホームページ上にもライター情報が記載されているので安心です。
取材・執筆はもちろんのこと、取材記事の内容の企画考案から任せられるのもポイントです。
https://webwriter-pro.co.jp/interview
取材・記事制作サービス 取材.biz
取材・記事制作サービス「取材.biz」は、株式会社ラユニオン・パブリケーションズが運営しており、ビジネス誌や企業広報、官公庁・自治体といった幅広い分野で豊富な実績を持つのが特徴です。
料金プランは明確に分かれており、シンプル・プランが5万円〜、スタンダード・プランが15万円〜、カスタム・プランが30万円〜となっています。なお、実際にインタビュアーが取材を行うのはスタンダード・プラン以上からです。
また、取材の目的やテーマ、文字数、記事本数などについて柔軟に相談できる体制が整っている点も大きな魅力といえるでしょう。
https://lunion.jp/services/services-edit-05.html
社員インタビュー記事で採用活動を加速しよう

社員インタビュー記事は、求人票や会社説明では伝えきれない「生の声」を提供することで、企業と求職者の“出会いの質”を高める非常に有効な手段です。応募者数の増加だけでなく、入社後の定着率アップや、社内外に対する企業ブランドの向上など、さまざまなメリットが期待できます。
ポイントは、「誰に何を伝えたいのか」を明確にしながら、インタビューする社員を選定し、記事の構成を工夫すること。そして、読者が社員や企業文化に共感してくれるよう、写真や動画などを使って“リアル”を演出することです。
現場の社員が自社について熱く語る様子ほど、読み手の心を動かす材料はありません。インタビュー記事を戦略的に活用し、企業の魅力を最大限アピールして、採用活動を加速させましょう。

・取材記事制作を作るうえでの不安が払拭された
・この資料で外注に反対の上司を説得できた

